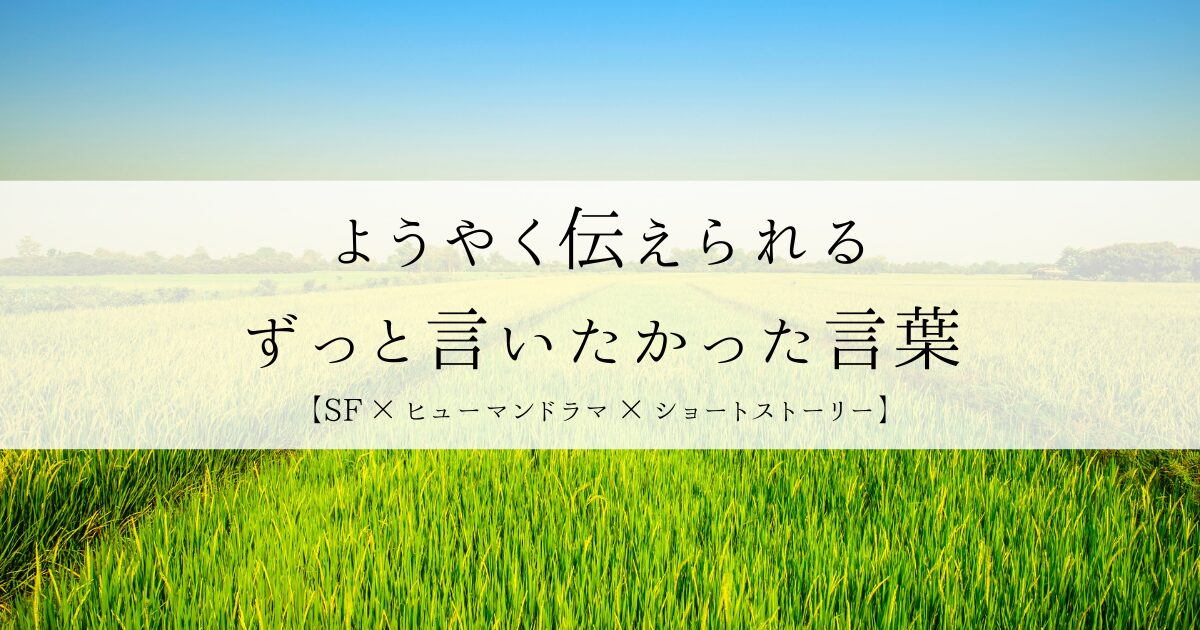こんにちは、松波慶次です。
SF ×ヒューマンドラマ×ショートストーリー『サマーエクスペリエンスー夏体験ー』の小説と朗読動画を載せています。
近年の猛暑は身体に堪えますが、夏が一番好きな季節です(^^)
ぜひ小説と動画、両方お楽しみください!
あらすじ
部下から「いろんな夏が体験できる」という〈サマーエクスペリエンス〉の噂を聞いた間口克則は、チラシが配られているという駅の地下に行ってみた。
すると本当にチラシが配られていて、体験できる場所に行ってみることに。
「昭和の夏」を体験することにした間口は、気が付くと夏の日差しが眩しい、田んぼが広がる場所に立っていた。
「かっちゃん?」
声をかけられて振り返ると、そこには知っている顔があったーー。
小説『サマーエクスペリエンスー夏体験ー』
文字数:約6200字
買い物袋をテーブルに置くと、ネクタイを緩めて椅子に座る。徒歩5分ほどの距離にあるコンビニへ行くだけでも噴き出した汗をハンカチで拭い、エアコンのありがたさを感じながら袋から弁当を取り出した。
オフィスのウォーターサーバーから持ってきた水を喉を鳴らして飲み、弁当の蓋を開けて黒ゴマの乗った白米を口に運ぶ。
「部長ーまたコンビニ弁当ですか? いい年なんだから、自炊して健康志向になったほうがいいですよー」
「そういう黒田だって、コンビニ弁当じゃないか」
「俺はいいんです。まだ若いんで」
30代半ばの黒田は褐色に焼けた肌のなかでは目立つ白い歯を見せて笑うと俺の前の席に座った。13時半。昼時を少し過ぎた社員食堂には俺と黒田しかいなかった。
「それにしても、また焼けたんじゃないか? この間の土日もサーフィン行ったの?」
「行きましたよー。だって夏といったらサーフィンでしょ」
黒田は唐揚げを口にほおばる。最近は脂っこいものが胃に来るようになった。鮮やかなピンク色の鮭に箸をつける。
「元気でいいな。俺は特に、夏といったらみたいなものはないな」
「なんか夏の思い出ないんですか? 夏といったら祭り! とか、キャンプ! とか」
「うーん。そうだな。黒田みたいに毎年恒例って感じのはないなー」
「部長、なんか寂しいですね。そんなだからいまだに彼女できないんですよ」
「もう50の男に何言ってんだ。それに余計なお世話」
「あ、だったら部長。〈サマーエクスペリエンス〉っての、やってみたらどうですか?」
「さまーえくすぺりえんす?」
「直訳すると〈夏体験〉。最近A駅の地下鉄の改札近くでチラシが配られてるみたいで、なんでもいろんな夏を体験できるみたいですよ」
「なんだそれ」
「俺も同期からちょこっと聞いただけなんで詳しく知らないんです。ネットで検索すると一応ヒットはするんですが、チラシが配られてるーくらいで、全然わかんないんですよね。部長、チラシもらいに行ってみたらいいじゃないですか」「怪しいな。新しい宗教か何かか?」
「さぁ。でも、チラシもらえたらラッキーですよ。本当に時々しか現れないみたいだし。なんか楽しい夏、体験してみたらいいじゃないですか」
ヘラヘラと笑う黒田が空になった弁当を袋に詰めるのを見ながら、鮭の最後の一切れを口に放り込んだ。
*
帰り道とは違うA駅の地下に来ても新鮮味はなく、ごった返す人の波にどこも変わらないなと辟易した。
別に黒田のいうようにチラシ配りに出会わなくてもいいという気持ちで来てみたが、改札まで行くと柱の裏で紙束を抱えている白衣を着た女性を見つけて、まさかと思い近づいてみた。
「こんにちはー。もしよければどうぞー」
女性からチラシを一枚受け取る。〈サマーエクスペリエンス。あなたの気になる夏を体験してみませんか?〉という文字と虫取り網を持った少年、ひまわりが描かれていた。
「あ、あの」
「はい?」
女性の大きな瞳が俺を見つめる。ハーフなのか、黒というより灰色がかっていた。
「これは、どこでーー」
「あ、お客さん、気になります? お時間あるときにでもここに来てください」
細い指で指し示されたのは、俺が持つチラシの右下。小さく住所が書かれていた。営業時間や電話番号の記載はない。
「明日は空いてますか?」
顔を上げるとそこには誰もいなかった。辺りを見回しても、駆け足のスーツ姿の男や気だるそうな若者ばかり。一瞬にして人混みに紛れてしまったのだろうか。ただ手の中の紙の感触だけは確かだった。
*
もしサマーエクスペリエンスをやるなら次の日にしようと決めていた。休みだったし特に予定も入っていなかったからだ。といっても、もともと独り身で趣味もない男。仕事の日じゃなければ基本的に空いている。
一応動きやすい格好で行った方がいいかと思って半袖シャツにジーパンにした。金額もわからなかったから5万円くらいを財布に入れ、スニーカーを履き、チラシに書かれていた住所に向かった。
辿り着いた場所は、外壁がいまにも剥がれ落ちてきそうなほどボロボロのビルだった。ここの3階。エレベーターはない。
踊り場に2部屋ずつ向かい合ってあるが、どこもテナントは入っていなさそうだった。ところどころ剥がれた階段を上り、目的の部屋へ。
看板はない。チャイムを鳴らす。
「はーい」
聞き覚えのある声が聞こえたと同時にドアが開かれた。
「ようこそ、サマーエクスペリエンスへ」
チラシを配っていた女性。いまも白衣だ。
「あの、これってどういうーー」
「とりあえず中へどうぞ。ご説明します」
またしても遮られたが、今度はきちんと説明してもらえるらしい。
人ひとりが立てるほどの玄関で靴を脱ぎ、細い廊下を進むと開けた空間に出た。
2メートルほどはある卵みたいな白い機械に、何本もの導線がつながれている。
その正面にはモニターやパソコンが置かれたデスクと、白衣を着た30代くらいの男がいた。
「いらっしゃいませ」
「所長、この人体験希望です」
「いつの夏がいいですか? 昭和、平成、令和。いまから50年後の夏も体験できますよ」
「ちょ、ちょっと待ってください!」
無表情で淡々と話し出す男を手を振って制止すると、何か問題でも? というように小首を傾げられた。
「あの、サマーエクスペリエンス、これ初めてやるので、まずは説明してほしいんですが」
「ナギサくん、まだ説明してないの?」
「中入ってからしようと思ってまして」
ナギサと呼ばれた女性が舌を出して笑うと、男は後頭部をかいて口を開いた。
「サマーエクスペリエンスは、お客さんが好きな夏、過ごしてみたい夏を体験できます。例えば、昭和の夏を体験して懐かしさを感じてもいいですし、未来の夏を先取りしてもいいです。で、どうしますか?」
「待ってくださいよ! 説明それだけですか?」
「はい。で、どうしますか?」
「お金は? 体験料とか必要じゃないんですか? あとは仕組みとか」
「無料です。仕組みは、凡人に言っても分かりません。お客さんが決めるのはどの夏を体験したいかです。やる気がないならお引き取りください」
機械と話しているかのように埒が明かない。ナギサを見ると男の隣でパソコンをいじっていて、すでに俺なんか見ていない。説明するっていったくせに!
詐欺かもしれない。承諾した途端大金をせびられるかも。だけど怪しい契約書もないから売買契約を立証するものもない。騙す気ならもっと甘い言葉を吐いてくるはずだ。
「……しょ、昭和の夏で」
黙り込む俺をじっと見つめていた男からのプレッシャーもあって、体験へ踏み出した。男はようやく口を開いた俺に安堵するでも頷くでもなく、無表情のまま手元のスイッチを押した。
卵の上部が無機質な音を立てながら開く。座り心地がよさそうな椅子が出てきた。
「そこに座っててください。すぐに始まります」
男は目の前のパソコンをいじり始める。
言われるがまま椅子に座ると、卵が閉じた。内からだと外が見えるようで、せっせとパソコンを操作する2人が見えたーー。
*
田んぼに囲まれた田舎道。暑い日差しが降り注ぐ。見上げるとすべてを灼きつくさんとする大きな太陽が照っていて、思わず額に手をかざした。
「ここは……」
辺りにはなにもない。ビルも、民家も、駅も。田んぼと、遠くに緑が眩しい山があるだけ。
チリンチリン。軽い音色。
振り向くと、木製の小屋があった。表には同じく木製のベンチ。軒先には〈氷〉と書かれた旗が風に揺れている。なかを覗くと、たくさんのお菓子が棚に並べられていた。
駄菓子屋。子どものころ、よく小銭を握りしめて買いに来ていた。最近はめっきり見かけなくなった。
「かっちゃん?」
吸い寄せられるようになかに入ろうとしたとき、夏の青空によく響く高い声に引き留められた。
声のした方に首を回すと、白い半袖シャツに短パン姿で、虫捕り網を手に持ち、虫カゴを肩から斜めに掛けた男の子がいた。
「こう、いち?」
「あ、やっぱかっちゃんだ! こんなところでなにやってんだよー」
孝一は俺に駆け足で近付くと、腕を引っ張りベンチに座らせた。そのまま駄菓子屋のなかに入り、おばちゃんアイス2つちょーだいと元気に叫んでいた。
日陰のベンチは涼しく、流れていた汗がひんやりとする。ポケットからハンカチを取り出して拭くとシミができた。やけにリアルだ。これが〈体験〉なのか。
「かっちゃん、これ。アイス。ちょうど小遣い入ったから、俺のおごりな」
アイスを差し出しながら孝一が隣に座る。
「あ、あぁ。ありがとう」
「さっきお前んち行ったけどいなかったから、ひとりで虫でも捕りいこうかと思ったんだよ。まさかこんなところにいるなんて」
少し不満そうに口をとがらせながらもどこか楽しそうな孝一は、棒アイスの包みを開け一口かじった。
受け取ったアイスは子どものころよく食べていたやつだ。牛乳の味が濃くて好きだった。
溶けてしまう前に、俺もアイスを食べる。冷たさが歯に沁みた。
「孝一、よく俺だってわかったな。もう50のおっさんなのに」
「は? 何言ってんだ? 俺と同じ9才だろ? どこがおっさんなんだよ」
アイスを一瞬にして食べ終えた孝一はハズレだーと悔しそうに零しながら置かれていたごみ箱に棒を捨てていた。
どうやら俺は、この体験のなかじゃ9才の間口克則らしい。俺も〈ハズレ〉と書かれた棒をごみ箱に捨てると、唐突に手を握られた。
「じゃ、行こうぜ!」
「え? どこに?」
「虫捕り! いつもの場所な!」
走る。山に向かって。夏の太陽は容赦なく、俺たちを照らしてきた。汗がしたたる。久しぶりに走った。ちょっとだけ湿った夏の空気が肺に入り込む。
楽しい。
*
網はひとつしかないから、捕まえる役とカゴを持つ役でわかれた。孝一がミンミンジージーとうるさいセミを捕まえて、俺がカゴを開けて受け取る。カゴはすぐいっぱいになった。
「よーし、次はあいつだ!」
透明な羽に大きな体。クマンゼミだ。足音を立てないように忍び寄る孝一に、がんばれ! と後ろから小さく声援を送る。
孝一が小石につまずいて小さく悲鳴を上げた途端、セミが飛んだ。少量の液体が孝一の顔にかかる。
「ぶへっ! きったねー! しょんべんかけられたわー!」
「きったねーな! こっち寄んなよ!」
「お前もしょんべんまみれにしてやるー!」
孝一が顔を拭きながら追いかけてくる。俺は大きな木に回り込み、お互いに相手の様子を伺いながらクルクルと回った。
ひとしきりゲラゲラと笑って動き疲れたところで、孝一は足元を探り始めた。
「どうした?」
「長い枝ないかな?」
「なんで?」
「川行こう。そこで釣りやろうぜ」
「釣りってったって、糸は?」
「実は持ってる。ポケットに入れてあんだ」
ポケットに手を突っ込むと、自慢げに白い糸を取り出した。
「お前、そういうとこ用意周到だったもんな」
「じゃ、とっとと枝見つけて川行くぞー!」
手に持ちやすく、長い枝を2人バラバラになって探す。釣り竿とまではいえないけど50cmほどはある簡単には折れない木の棒を2本見つけた。
孝一に自慢げに見せると跳ねて喜び、そのまま川に駆けていった。
ゴツゴツした岩が転がる川辺は、決して歩きやすくなんかない。スニーカーの側面に岩が当たり、いくつも汚れをつけていった。
川の流れは速い。川のなかにも大きな岩がいくつもあるからあちこちで岩に水がぶつかり渦を作っている。
「じゃ、糸つけて……」
ポケットから糸を取り出すと、孝一は枝の先に器用に結んでいった。
「エサは?」
「いらない。このままやる」
白い糸をぶら下げた枝を振り、川へ向かって投げる。俺もならって、ふたりで魚がかかるはずのない糸を垂らしたまま並ぶ。
ゴーゴーと川の流れる音。セミの鳴き声。風に揺れ、木々の葉が擦れ合う。
懐かしい風景。懐かしい匂い。懐かしい感情。懐かしい友達。
静かな時間がゆっくりと流れる……。
「……あのとき、助けられなくてごめん」
カラカラの喉から絞り出した言葉は、川の流れにさらわれるほど小さかった。孝一に聞こえただろうか。
もう一度言おうと枝を握る手に力を込めたとき、「気にしてないよ」と落ち着いた赦しが返ってきた。
「別に、かっちゃんが悪いわけじゃないし。俺が川に入ってったのが悪いんだから」
あのとき、いまと同じように孝一と川に遊びに来ていた。枝じゃなく釣り竿を持って。餌も用意して。いつもどおり。俺たちの夏。
孝一の竿に魚が引っかかった。川の流れか、川底の岩に引っかかったのか。なかなか魚を釣り上げられなくて、孝一は川に入っていった。
体が傾いたと思ったときには、俺の視界から孝一の姿は消えていたんだ。名前を呼んでも返事はなくて、それでも名前を呼び続けて、ようやく事態の深刻さに気付いて家に駆けていった。
警察や救急隊員の捜索はすぐに終わった。孝一が姿を消した位置から数十メートル下流の岩場に引っかかっていたのを引き上げられたとき、びしょ濡れなのに顔を拭わず、悪態もつかない親友に死を実感して涙と鼻水が止まらなかったことを覚えている。
「いや、俺がもっと早く助けを呼んでいれば、孝一はーー」
「俺は」
力強い声と視線を感じて顔を上げる。孝一と同じ高さで目線が合った。
「かっちゃんとあの日遊んだこと、後悔してない。だから、もう俺のことで自分を責めないで。俺との最期の夏じゃなくて、かっちゃんは自分の夏を生きて」
くしゃっと笑う。俺は笑えなかった。ずっと心の奥底にあったじっとりとした苔のような感情の正体がわかって、溶けて、涙が溢れ出てきた。
「孝一……」
「時間だよ、戻りな」
孝一が、青空が、鮮やかな緑が、憎かった川が白い光に包まれる。手を伸ばしたけど、短い腕は孝一には届かず、夏の熱気を掴んだだけだったーー。
*
「サマーエクスペリエンス、終了です」
明るい声に目を開ける。機械の蓋が開いていて、すぐ隣にナギサがいた。
頬や目元に何かが触れている感覚があって触ってみると、水滴が指先についた。
機械から降りる。パソコンの前に座る男と目が合った。変わらずの無表情だ。
言いたいこと、聞きたいことが喉元まで出かかったが、息を吐いたらすべて消えた。
すでに少し湿っていたハンカチで頬と目元を拭う。
「どうしますか? 令和の先、未来の夏も体験できますけど?」
ナギサが俺を見上げた。灰色がかった瞳が楽しそうに輝いている。
「いや、大丈夫です」
「えー、いいんですか? なんなら弥生時代の夏とかも体験できますけど」
太陽の光を受け熱を帯び続ける滑稽な姿の埴輪を思い浮かべて苦笑が漏れた。
「もういいんです。目の前にある夏を、大切にしていきたいので」
ナギサと男に会釈をして出口に向かう。後方からキーボードを叩く音が聞こえてきた。
*
「部長ー。前言った〈サマーエクスペリエンス〉、試したくて何度も駅に行ってるんですけど、全然チラシ配ってる人いないんですよー。ガセネタだったのかな?」
黒田がチキン南蛮弁当を袋から出しながら愚痴る。俺は棒アイスを食べながら笑った。
「タイミングじゃないのか? 必要になったら現れるとか、さ」
「なんの必要になったらなんですか。それより、ちょっと肌焼けてません? 昼間の散歩は熱中症リスク高いですよ」「なんで散歩だと思ったんだよ。違うよ。釣りをね、始めたんだ」
「釣りですか?」
「あぁ。昔、友達とよくやってたんだ。川釣りなんだけど」
「へー。いいじゃないですか! 今度俺も誘ってくださいよ」
「もちろん。一緒に夏を楽しもう」
最後の一口をかじる。棒に書かれていたのは〈あたり〉の3文字だった。
朗読動画『サマーエクスペリエンスー夏体験ー』
動画時間:約21分半
あとがき
冒頭でも言いましたように、私は夏が一番好きな季節です。暑いのは大変ですし、汗もかきたいわけじゃないですが、なんだか「活発」な季節で、お祭りや水のアクティビティなど「イベント」も多い感じがして、テンションが上がるんですよね。
近年の猛暑は「楽しい夏」を「危険な夏」に変えていて、行動量が制限されがち……。そこが残念なところです。難しいとは思いますが、少し前の、一般的な「夏」の暑さに戻ってほしいですね……。
最後までご覧いただきありがとうございました! ほかにも無料で読める小説を掲載しているので、ぜひそちらもご覧ください(^^)