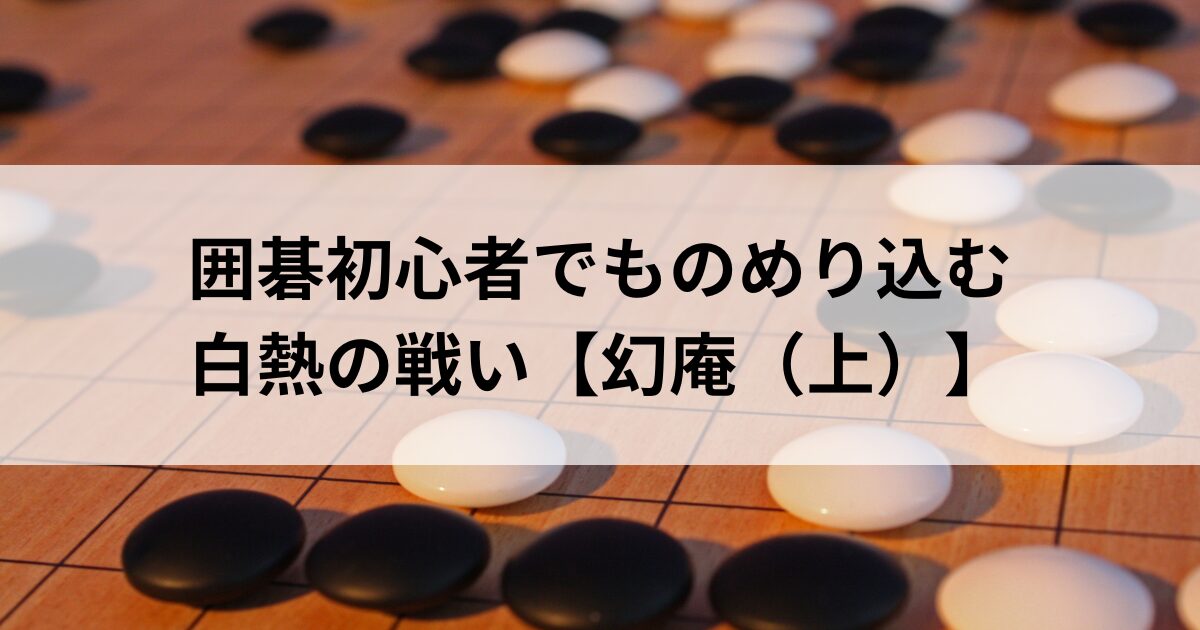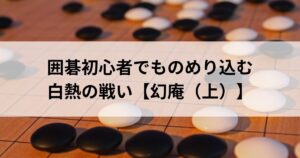こんにちは、松波慶次です!
今回は、『幻庵(げんなん)』の上巻のあらすじと感想をまとめています。
囲碁って奥深い……。
以下ネタバレ注意です!
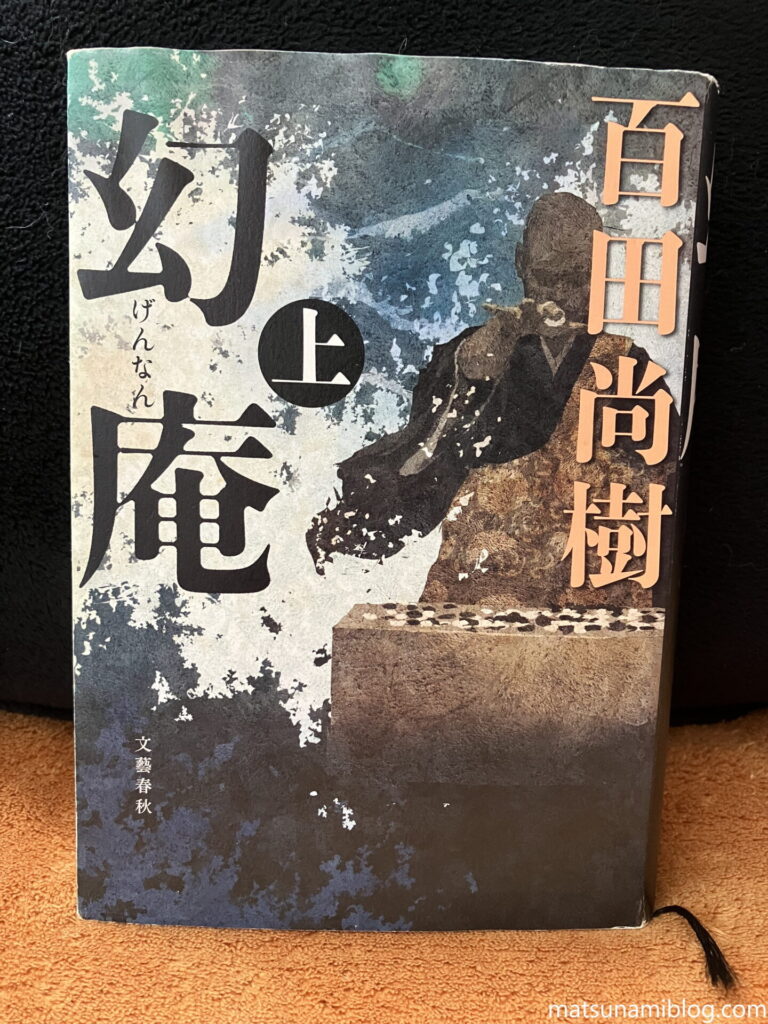
タイトル:幻庵(上)
著者:百田尚樹
あらすじ
江戸時代。のちに囲碁界に名を轟かせる「幻庵(げんなん)」の幼少期からを、ほかの囲碁の強者(つわもの)たちの成長や人間関係とともに描いた物語。
上巻では、幻庵が井上家の跡目となるところまでを描いている。
感想
私は武術の稽古に通っているのですが、先生がよく本を読む方で、いらなくなった本を私にたびたび譲ってくれます。
そのなかの一冊が本作。百田尚樹氏の名前は知っていても、この作品は知らない。ページを開いてみると、碁盤の解説図や囲碁に関する言葉が作中に出てくる。冒頭の主要登場人物の説明を見ると、〇世とか当主とか書かれてるし、名前からして現代の話ではない。
おぉ、これは歴史物の囲碁の話か。こりゃ面白そうだ。
ということで読み始めたら、囲碁初心者(過去に一度だけやったことがある)でルールや戦略にまったく詳しくない私でも熱くなるほど緊張感がある物語でした。
まず冒頭、物語に入る前に囲碁のすごさが伝わる解説があるのですが(AIとの対局やAIが囲碁で勝つまでの工程など)、それを読んだだけで「囲碁すげー!!」と興奮。
将棋やチェスなどと異なり、囲碁は右脳の競技であるなど、AIが勝てない(勝つのが難しい)背景等が記されていて、囲碁という競技の面白さ、奥深さを実感しました。
もちろん、それは物語のなかでも。多くの囲碁棋士たちの対局が描かれているのですが、一手打つのに6時間考える、30時間以上もぶっ通して囲碁を打つなど、難しさ、楽しさ、一瞬の判断の誤りの影響力などが読むたびに伝わってくるので、囲碁はただの遊びではなく、まさに真剣勝負(命を削る)なのだと感じます。
「囲碁士は親の死に目に会えない」という言葉も、本作で初めて聞いた(知った)のですが、殿様の前で囲碁を打つことがあり、当日殿様を飽きさせないようスムーズに囲碁を打つため事前に勝負をする際、囲碁を打っている屋敷からは終局するまで出てはならないというのが背景にあるようで、面白いと思いました。
囲碁に関する歴史的、人物的なもろもろの知識も蓄えられます。
登場人物でいうと、元丈と知得の仲の良さ、ライバル関係の良さが印象的で、やはり力をつけるのにライバル(好敵手)の存在は大きいのだと感じました。
知達が死んでしまったことは悲しく、ライバルであった幻庵の心中はどれほどのものだったのかと、想像すると苦しくなります。
丈和は、年齢やブランクがあっても必死に頑張り、ついには跡目となったことがすごい。人間、懸命に打ち込めば世間一般的にいう「伸び盛りの時期」や「ちょうどいい年齢」などを覆すほどの力を発揮するものだと、丈和の諦めない心や囲碁への熱意に感動しました。
物語の最後、元丈以外の5人(仙知(知得)・因淑・丈和・元美・安節(幻庵))が今後大きなことに巻き込まれる旨の文章があって、人を魅了するこの5人に何が待ち受けているのか、下巻が楽しみです。